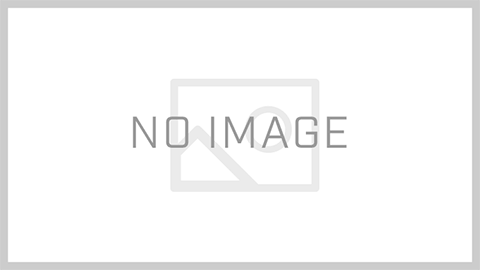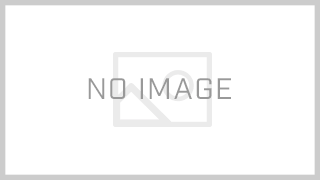父の入院をきっかけに「後期高齢者医療制度」を調べてみたら、意外と知らないことだらけでした【わかりやすく解説】
こんばんは。めいちゃんパパです。
先日、後期高齢者である父が病気で入院することになりました。入院の時に一番気にするのは医療費のことですよね。そこで、「後期高齢者医療制度」についていろいろ調べてみました。
ちゃんと調べてみると、この制度ってとても大事で、知っておくと安心できるものだと感じました。
今回は、同じようにご家族やご自身のことで気になっている方に向けて、「後期高齢者医療制度って何?」という基本から、保険料や医療費、扶養の話までを、私なりにわかりやすくまとめてみました!
◆ 後期高齢者医療制度ってなに?
「後期高齢者医療制度」とは、75歳以上の方(または65歳以上で障がいがある方)が対象となる、公的な医療保険制度です。
簡単に言えば、
👉 75歳を超えると、それまでの健康保険とは別の仕組みに切り替わるということ。
制度の正式名称はちょっと堅苦しいですが、内容は「高齢者が安心して医療を受けられるようにする」ためのものです。
◆ 誰が加入するの?
-
75歳以上のすべての人が、自動的に加入
-
65歳以上で障がいがある方も、申請により加入可能
私の父も、75歳になったときにこの制度に自動的に切り替わっていました。
◆ 75歳になると「扶養」から外れるって知ってましたか?
これは私も今回初めて知ったのですが、
👉 75歳になると、それまで家族の健康保険の「扶養」だった人も、扶養から外れてしまうんです!
たとえば父は、以前は私の会社の健康保険に「被扶養者」として入っていたのですが、75歳の誕生日を迎えた翌月からは「後期高齢者医療制度に本人として加入」になっていました。
つまり、
-
扶養から外れる
-
自分の保険証(後期高齢者医療保険証)を持つ
-
保険料も自分で支払うことになる
…という流れになります。制度上の仕組みとはいえ、ちょっとびっくりでした。
◆ 保険料ってどのくらい?どうやって払うの?
後期高齢者の保険料は、以下のように計算されます。
-
均等割:みんな一律にかかる金額
-
所得割:年金や収入に応じて決まる部分
多くの場合、年金から天引きされる仕組みになっています。
(父の場合もそうでした)
※年金額が少ない場合や希望がある場合は、口座振替など別の支払い方法も選べます。
◆ 病院での医療費負担は?
病院の窓口で支払う自己負担割合は、
-
原則1割
-
一定以上の所得がある方は2割または3割
となっています。
うちの父は年金生活で収入が少ないので「1割負担」でした。
10,000円の医療費なら、1,000円を支払う形です。
◆ 高額療養費制度もあります!
入院や手術などで医療費が高額になってしまった場合には、「高額療養費制度」で自己負担額の上限を超えた分が払い戻されます。
これも収入によって上限が異なるので、入院が長引いたときなどは必ず確認したほうが安心です。
入院費が高額になった場合に使える「高額療養費制度」については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉 🔗【父が75歳で入院】高額療養費制度を徹底調査!
◆ 財源ってどこから出てるの?
後期高齢者医療制度の財源は、3つに分かれています。
-
本人が支払う保険料
-
**現役世代(会社員など)**が支払う支援金
-
国・都道府県・市区町村などの公費
つまり、社会全体で支え合っている制度なんですね。
◆ まとめ:知っておくと安心できる制度でした
父の入院は突然のことで本当に焦りましたが、こうして制度について調べていくと、**「知らなかったら損をしていたかも…」**ということがたくさんありました。
✅ ポイントまとめ
-
75歳になると後期高齢者医療制度に切り替わる
-
それまで家族の扶養に入っていても、外れる
-
保険料は年金などから支払い。自己負担は基本1割
-
高額療養費制度や公的支援もあるから安心!
もしご家族に後期高齢者の方がいる方、これから対象になる方がいる方は、ぜひ一度「保険証の種類」「保険料」「負担割合」などを確認しておくことをおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
皆さんのご家族も、安心して医療が受けられますように。